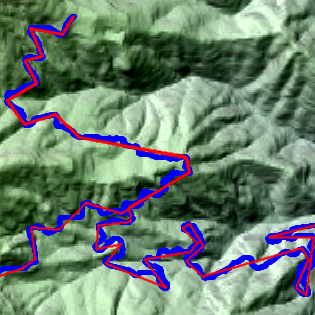どこからでもWolfram Engine + JupyterLabにアクセスできる環境を構築する
無料で使えるWolfram EngineをJupyterLabと組み合わせることでMathematicaっぽいノートブック環境を構築できる。
ただ、既存のやり方では環境構築に結構手間がかかるほか、起動時に毎回トークンをブラウザにコピペする必要があった。
そこで認証機能はCloudflare Accessに任せることで起動時のトークン入力を省略し、 またCloudflare Tunnelと組み合わせることでどこからでもアクセスできるようにしつつ、 docker composeを使ってコンテナに格納してしまうことで可搬性を高めた環境を構築してみた。